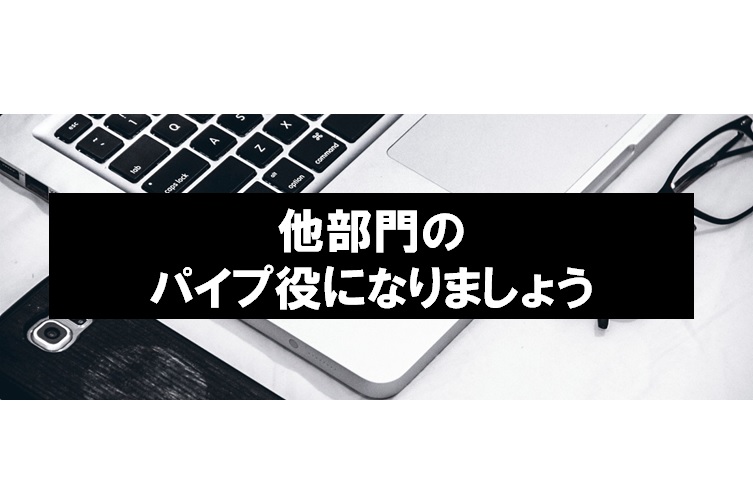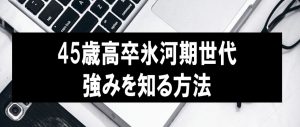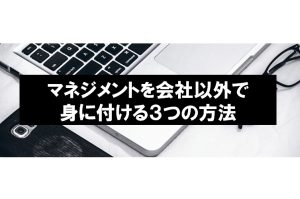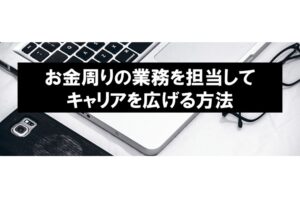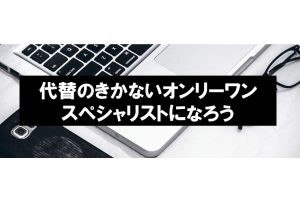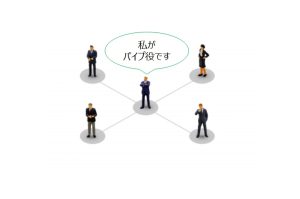
はじめに
会社で働く中で、「他部門とのやり取りが面倒だ」と感じたことはありませんか。
部署ごとに担当が分かれているため、ちょっとした確認でも手間がかかります。
しかし、この「面倒な部分」こそがチャンスです。
他部門とのパイプ役になることで、仕事が円滑になり、自身の評価や信頼も大きく高まります。
パイプ役に必要な力は特別なスキルではない
パイプ役と聞くと、特別なスキルや高い社交性が必要と思われがちです。
実際には、必要なのは「ちょっとした勇気」と「気遣い」です。
最初の一言をかける勇気、メールを送る気遣い、それだけで関係は築けます。
私自身、決して仕事がずば抜けてできるタイプではありませんが、この姿勢だけで人とのつながりを増やすことができました。
具体例:営業が他部門と連携する場面
例えば営業職の場合、価格交渉を進めるためにはさまざまな情報が必要です。
- 原価なら購買やバイヤー
- 加工や工程なら生産技術や設計
- 材料なら開発や資材部門
- 生産性や作業時間なら工場
これだけで最低でも5つの部署と関わることになります。
他部門と顔見知りになっておけば、必要な時にスムーズに情報が集まります。
最初の一歩は「挨拶と雑談」
私が実践してきたのは、まず「初対面で挨拶」することです。
「これからお世話になりますので、よろしくお願いします」と一言添えるだけで、相手に安心感を与えられます。
初回はメールよりも直接の挨拶や電話のほうが印象に残ります。
その後は、週末の出来事や天気など、仕事以外のちょっとした雑談も交えるようにしました。
こうした小さな積み重ねが「つながり」を育てます。
私の体験談:パイプ役で広がった世界
私はこれまで営業、設計、システムなど複数の部門に関わる仕事を経験してきました。
正直に言えば、自分ひとりの力だけで仕事をこなせるほど優秀ではありません。
だからこそ、周りの力を借りる必要がありました。
営業時代には、見積もりに必要な情報を設計や工場から得るために頻繁に連絡を取りました。
最初は面倒に思われたかもしれませんが、定期的に顔を出すうちに「困ったらあいつに聞けばいい」と頼られるようになりました。
結果として、私が情報のハブとなり、部門をまたいで案件が進むようになったのです。
他部門からの相談が来るようになる
ある時には逆に、他部門から「営業で知っているのは君だから、ちょっと教えて」と相談されるようになりました。
自分の専門外でも、誰に聞けば良いかを知っているだけでも十分役に立てます。
このように「情報の中継役」として信頼を得られると、自然と周囲からの評価も上がります。
コミュニケーションが苦手でも大丈夫
「自分はコミュニケーションが苦手だから無理」と思う方もいるかもしれません。
私も最初から話すのが得意だったわけではありません。
それでも、「仕事だから」と割り切って少しずつ声をかけ続けるうちに慣れていきました。
雑談も、最初はぎこちなくても大丈夫です。回数を重ねれば自然になります。
情報の鮮度と説得力が増す
現場から直接情報を得られるようになると、その内容は鮮度抜群です。
机上のデータだけでなく、リアルな声を聞けるため、提案や交渉の際の説得力が格段に上がります。
「現場の担当者に確認済み」というだけで、発言の重みが違ってきます。
パイプ役がもたらすメリットとデメリット
パイプ役になることで得られるメリットは数多くあります。
- 仕事のスピードが上がる
- 情報の正確性が高まる
- 周囲から頼られる存在になる
- 部門をまたいだ人脈が築ける
- 評価や信頼につながりやすい
私は特に「人脈」が大きな財産になりました。
転職や異動の際にも、顔を覚えてくれていた人が声をかけてくれたり、助けてくれたりしました。
デメリットとしては、
- 仕事が増える、広がる
たくさんのつながりができるので、おのずと取り扱う情報が増えることによって
仕事が増えてしまいます。
まとめ
他部門とのやり取りは一見すると面倒ですが、それを積極的に担うことで大きな強みになります。
特別なスキルや社交性は不要で、必要なのは小さな勇気と気遣いだけです。
細い糸のようなつながりも、やがては太いパイプとなり、あなたの仕事を支えてくれます。
ぜひ、他部門とのパイプ役に挑戦してみてください。